
今年も種もみの準備から、去年までの反省を活かしてまず脱芒作業を行いました。
もちをつく"もちっこ"という機械を使って2度に分け各10分ほど回します。
それ以降は概ね昨年と同様に
http://www.notodesign.jp/ateie/blog/2015/04/47.html
塩水選と温湯消毒を行いました。
1週間から10日ほど水に漬けて発芽を待ちます。

2/25に金沢21世紀美術館で開催されていた木育キャラバンに行って来ました。
木育講演、木育ワークショップ、木組みの小さな木の家など、見たい、聞きたい、やりたい事満載。
午前中は木育講演と子どもたちが木のオモチャに触れられる木育キャラバンのチームに分かれて行動。
木育キャラバンコーナーでは、子どもたちは大興奮。次から次へと楽しそうなおもちゃを見つけて遊びます。もちろん喧嘩をしながら。
最初にはまったのは木琴すべり台。木の種類によって木の音色が異なります。木の玉が転がり落ちるようになっていて、組み合わせで曲を作れたりも出来るようでした。

一番下の娘も一生懸命玉を拾って高いところから転がしていました。

葉っぱの形をした薄くスライスしてある木。後ろにマジックテープが貼ってあり、ぺたぺたとつけたり外したり出来ました。

木のプール。 最初は躊躇していた娘も、中に入ってみればダイナミックに兄と戯れていました。

周りの子達に協力してもらい、木の風呂につかる長男。

木のオモチャに触れることが木育の第一歩ということでしょうか。
そんなこととも知らずに、ただただ楽しむ子どもたち。
それが大事なんでしょう、きっと。
そして、午後からは「木組みの小さな木の家」の組み立て、解体を見学。
畳3帖程の空間を木組みで作り上げていく様子を見ることが出来ました。
子どもたちも真剣な眼差しで出来上がりを見守りました。

大工さんが二人掛かりで目の前で組み立てていきます。

床には畳。

建具、壁、天井もつきます。

木はこのようにしっかり木組みで固定されています。

出来上がり後、子どもたちは中に入る許可が出て、木のオモチャで遊びました。

木組みの空間は1時間後には解体が始まりました。
解体は美術館の外から眺めることに。
木組みでは栓を使って固定しています。
木組みで建てているアテイエにも見える所に栓が何ヶ所かあり、家と一緒だねと子どもたち。
小さいスケールだったので、木組みの組み立てを見学するにはちょうどよかったかと思います。
今回、「木育」というキーワードでイベントに参加しました。
そこで改めて感じたのは、私たちが作りたい、地元の木を使った家、そして木組みの家は、「木育」でもあるということ。
うちの子どもたちは、アテイエで育ち、知らぬ間に木育をうけているということ。
地元の木を使い、木のある空間の良さを伝えることを、「木育」という観点からも出来るよう、私たちももっと学んでいきたいと思ったのでした。






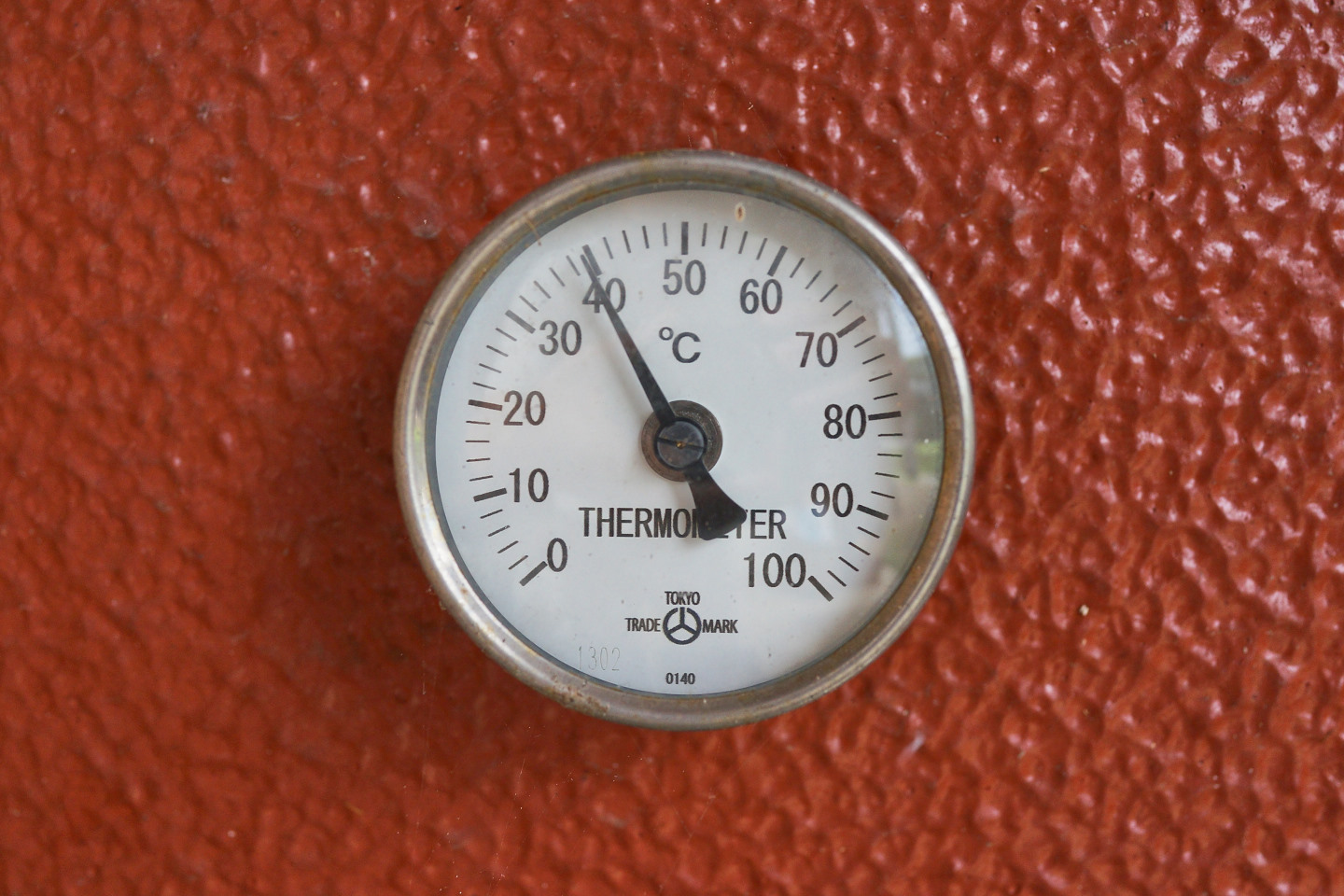

先日行われた「のとじま手まつり2016」
http://www.notodesign.jp/blog/2016/10/2016.html
今年はあらかじめ、子どもたちが日々大切に使える作品を手に入れようと思っていました。
今年、私が推選させて頂いたうるし劇場さん。
以前輪島のギャラリーでうるし劇場さんの作品を見かけ、いつか子どもにと思っていました。
もう10年以上のてに関わってきて、子どもたちはお腹にいるときも生まれてからも毎年のてに参加。
のての事で忙しくて忙しくて、子育てがおろそかになる時期も毎年秋にあったりして。
それでも子どもたちはのてを楽しみにしてくれています。
そろそろ、子どもに自分で選び、大切に使ってもらえるものをと。
毎日使うもので必要に感じていたのが「箸」です。
長男は、迷いながらもシンプルな朱の箸を選びました。
次男は、最初は中々選ばなかったものの、いつもの即決さで宇宙の図柄の箸を選びました。
1歳になる娘は選べないので私がドット柄を選びました。
イベントの日には、色と長さ、柄を選び、後日郵送してもらうことにしました。
名入れもして頂けるとのこと。到着を楽しみに待っていました。
それが本日到着!


柄も素敵なのですが、名入れしてもらった名前がすごく素敵です!
小学生の息子の漢字の名前はキリッとした感じがします。
年中の次男のやの字にある星マークがなんともほっこり。
そして、娘のどっとにポツポツと書かれた名前が、よちよちした感じでカワイイ。(ちよだからよちよちに見えているのかな、、、、)
そして、もう一つ。
長男にはごはん茶椀をと思い、輪島で漆作家をされている土田和茂さんのブースへ。
同年代で、同じ一年生のお子さんもいらっしゃるという土田さん。以前にもお会いしたことがあり、息子の茶椀は将来修理してもらえるようにと地元で、同年代の人がいいなと思っていたのです。

漆のお椀は、珍しく即決した息子。
選んだのはこちら。

大きくなって、1人暮らししてもずっと使っていってもらいたい。
修理が必要な時は、土田さんに会いにいってお願いしよう。
そう思って、1年生の息子には少々高いものでしたが、購入しました。
今はそのお椀で毎日新米を食べています。
のてを通じて、子どもたちがモノづくりを身近に感じ、人の手で作られたモノを長く大切に使えるようになってくれると嬉しいなと思う今日この頃であります。
うるし劇場→http://urushinamiko.jimdo.com
土田和茂→http://tsuchidaurushi.com
